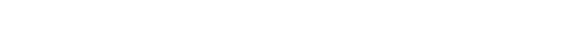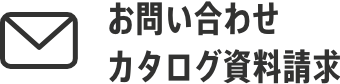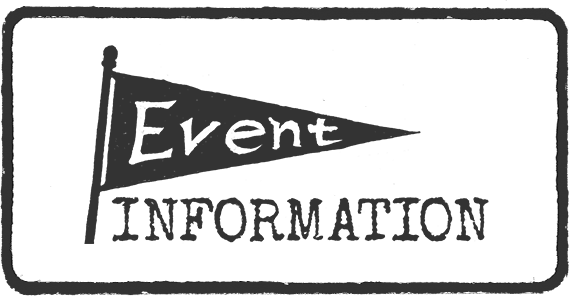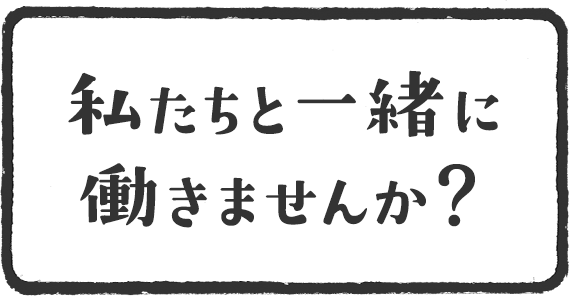最新記事

那須移住ブログ
那須移住ハーフビルドの家ルームツアー
2025.12.31

那須土地情報
20251221那須土地情報
2025.12.21

那須移住ブログ
那須移住、那須のどこに住むか?
2025.5.2

那須移住ブログ
那須移住、どこに住むか?part2
2025.4.29

ハーフビルドホームからのお知らせ
那須町Y様邸ルームツアー
2025.3.17

那須移住ブログ
4年越しの那須移住ハウス
2025.2.12
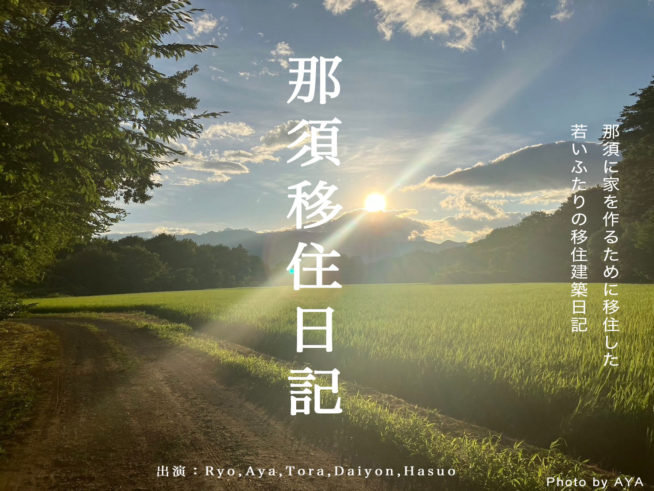
那須移住ブログ
那須移住日記 第6話 ハーフビルド
2024.11.18
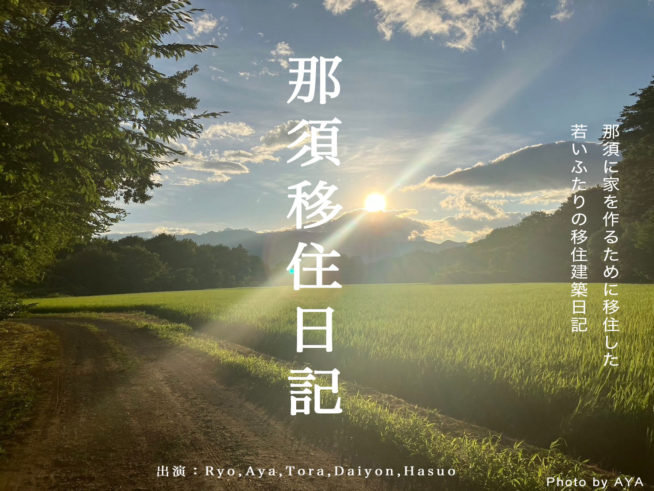
那須移住ブログ
那須移住日記 第5話 家の設計プランニング
2024.11.2

未分類
紅葉
2024.10.8
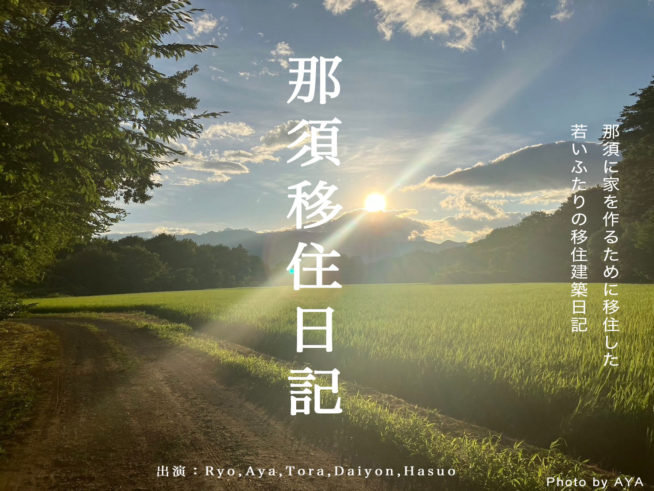
那須移住ブログ
那須移住日記 第4話 伐採工事と薪作り
2024.9.18
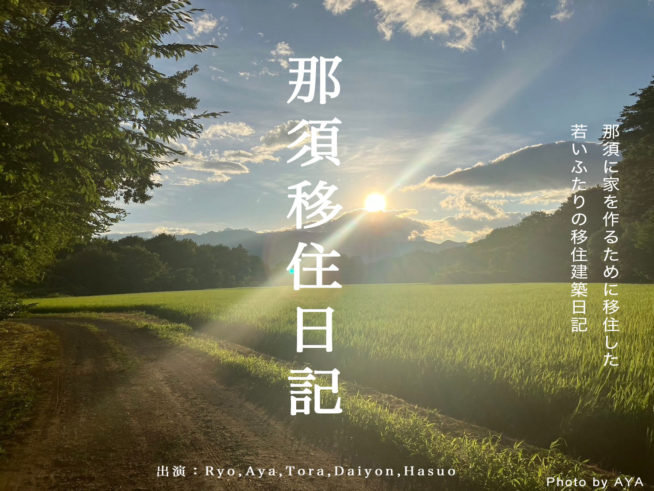
那須移住ブログ
那須移住日記 第3話 土地探し
2024.8.30
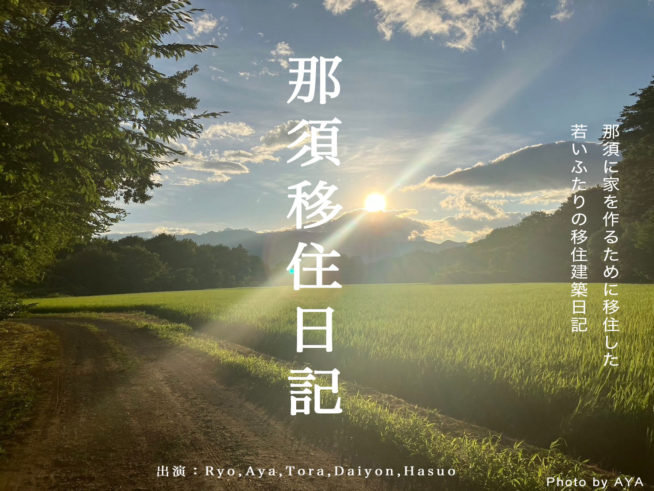
那須移住ブログ
那須移住日記 第2話 プロフィール
2024.8.28

那須移住ブログ
那須横沢の土地で家づくりがスタート
2024.8.27
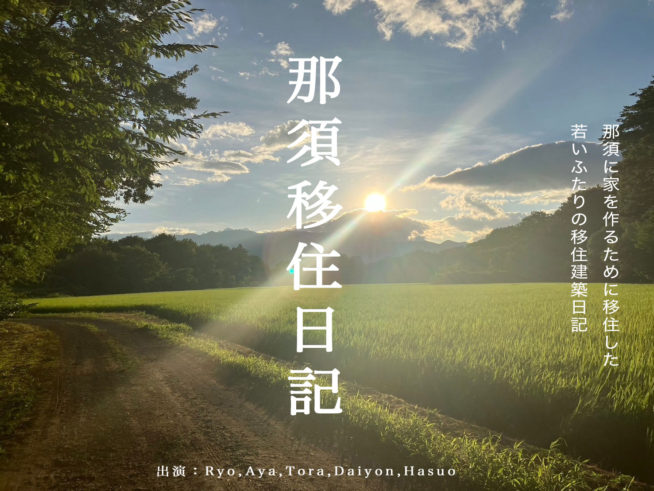
那須移住ブログ
那須移住日記 第1話
2024.8.25

那須移住ブログ
大盛況だった那須移住の家見学会
2024.7.13

那須土地情報
那須土地情報 – 小川が流れる夏でも涼しい高原分譲地
2024.6.18

那須移住ブログ
ヴァケーションレンタルブームについて
2024.6.16

DIYレクチャー
6月1日 第25回ハーフビルド創作教室開催しました
2024.6.5